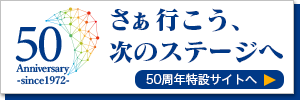防爆性能の記号表示にはどのようなものがありますか?
防爆性能を示す記号表示には、「構造規格」と「整合指針」の2つの規格で表示の違いがあります。
- (1)防爆構造の種類の表示
-
- 整合指針による防爆構造の場合は“Ex”を表示します。
構造規格については、“構造規格を示す記号”はありません。 - 防爆構造の種類
防爆構造の種類 構造規格 整合指針 耐圧防爆構造:内部で引火しても外部に影響を与えない構造 d d 内圧防爆構造:内圧で内部に爆発性ガスを侵入させない構造 f px,py,pz 油入防爆構造:電気部を保護液に浸した構造 o o 安全増防爆構造:火花や高温部の発生に安全度を増加した構造 e e 本質安全防爆構造:公的認証された爆発性ガスに点火しない構造 ia,ib ia,ib,ic 非点火防爆構造:通常時に点火源の火花を発生させない構造 n nA,nC,nR 樹脂充てん防爆構造:樹脂を充填して外部に点火させない構造 ma,mb ma,mb,mc 容器による粉塵防爆構造:粉塵が容器内に侵入しないようにした構造 - ta,tb,tc 特殊防爆構造:その他の方法で防爆が証明された構造 s -
- 整合指針による防爆構造の場合は“Ex”を表示します。
- (2)爆発性雰囲気の区分
-
国際整合防爆指針2015の場合、電気機器のグループは、爆発性雰囲気に応じて主に2つに区分されます。
グループⅡ:爆発性のガス又は蒸気が存在するおそれのある場所での使用を意図している電気機器
グループⅢ:爆発性の粉塵が存在するおそれのある場所での使用を意図している電気機器
※グループⅡとⅢは、爆発性雰囲気の性質に応じて、それぞれA、B、Cに細分類されます。
※グループⅠは炭鉱粉塵用で坑気の影響を受けやすい鉱山での使用を意図する機器なのですが、労働安全衛生法の下での検定対象外とされています。 - (3)爆発性ガスの爆発等級/グループ分類と発火度/温度等級
-
一般に工場でよく使われる代表的な爆発性ガスについて、構造規格の爆発等級と発火度及び整合指針のグループの分類と温度等級を表にしています。
取り扱われている爆発性ガス種類に合わせて、適応する防爆電気機器をご使用ください。■ 爆発性ガスの爆発等級(グループの分類)と発火度(温度等級)の表  ※爆発等級3において、3aは水素及び水性ガスを、3bは二硫化炭素を、3cはアセチレンを対象とし、3nは爆発等級3のガス全てを対象とします。
※爆発等級3において、3aは水素及び水性ガスを、3bは二硫化炭素を、3cはアセチレンを対象とし、3nは爆発等級3のガス全てを対象とします。
※整合指針のⅡBの下線付のガスは、構造規格では爆発等級1に含まれます。 - (4)粉塵の種別とその区分
-
粉塵防爆構造の電気機器については、粉塵の種別で分類されています。
■ 粉塵防爆のグループ(整合指針) 細分類 定義 構造規格の分類との対応関係 代表的な物質 ⅢA 可燃性浮遊物(繊維を含む可燃性の固体粒子であって公称粒子径が500μmを超えるもの) ”可燃性粉塵”のうち繊維を含み公称粒子径が500μmを超えるもの 繊維を含む固体粒子 レーヨン、綿、サイザル麻、ジュートなどの繊維 ⅢB 非導電性粉塵(公称粒子径が500μm以下かつ電気抵抗率が1,000Ωmを超えるもの) ”可燃性粉塵”のうち公称粒子径が500μm以下の非導電性粉塵 極小の粉体 穀物粉、砂糖、トナー、合成樹脂粉など ⅢC 導電性粉塵(公称粒子径が500μm以下かつ電気抵抗率が1,000Ωm以下のもの) ”爆燃性粉塵”ならびに可燃性粉 じんのうち公称粒子径が500μm以下の導電性粉塵 極小の金属粉 カーボンブラック、アルミニウム 、マグネシウムなど - (5)機器保護レベル(EPL:Equipment Protection Levels)
-
点火源となる可能性に基づいて機器に割り当てる保護レベルのことで、爆発性ガス雰囲気および爆発性粉塵雰囲気の違いに応じて区分されます。
整合指針(Ex指針)の2015年度版より表記されています。
■ 機器保護レベル(EPL:Equipment Protection Levels) 保護レベルの定義 グループ EPL(記号) 対応するゾーン 非常に高い保護レベル Ⅱ Ga 0 Ⅲ Da 20 高い保護レベル Ⅱ Gb 1 Ⅲ Db 21 強化された保護レベル Ⅱ Gc 2 Ⅲ Dc 22